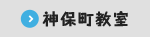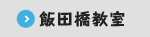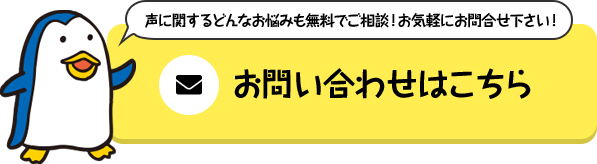シブイオンガクスタヂオでは、ご年配の方にむけて、嚥下力向上と、認知症対策となるコミュニケーションのトレーニングを実施しています。
ボイトレと嚥下についての関係性や、認知症対策になりうる有効性を、以下に記載しますので、是非気になる方は読んでみてください。
また、読んだうえで、対策をしたいと感じた方は、お気軽にお問合せください。
ボイトレと嚥下(飲み込むこと)の関係について。
喉の筋肉と嚥下
突然ですが、人生で生死にかかわる筋肉、なんだと思いますか?
それは、心筋、肺の筋肉、そして喉の筋肉だそうです。喉の役割は「呼吸」「発声」「嚥下(飲み込むこと)」です。発声で使う筋肉(舌や声帯などの喉頭の周囲筋)は嚥下筋とも言われ、嚥下とも関連しているのです。嚥下とは、食べ物を飲み込むこと。
ものを食べる仕組みとしては、摂食(口に食べ物を運ぶ)→咀嚼(噛む)→嚥下(飲み込む)の順に行います。
聞きなれない言葉が多く難しく感じるかも知れませんが、食べ物を体内に送り込む順序としては以下のような仕組みになっています。
1 食べ物を噛んで舌を上に押しあてて食べ物を食道へ(この時「
2 舌が上がると、
3 同時に声帯も食べ物が入らないよう気管をふさぐ
4 食道が上がってきて、そこに食べ物を送り込む
言い換えると、食べ物が食道に流れていくのではなく、
嚥下機能が弱ると見られる症状
嚥下に関わる声帯や喉の筋力が落ちると、食べ物を飲み込むとき気管をピタッと閉じられなくなり、異物が入って「誤嚥性肺炎」の原因になります。
誤嚥性肺炎は60代以降の喉の力が弱くなった人に発症しやすいと
若いうちは咳などで気管の中に異物が残らないように吐き出すこと
嚥下に関わる筋力が低下して見られる症状の、例を挙げます。
声の雰囲気が変わった / 食事中むせるようになった / 咳払いが増えた / 寝ていると急に咳込むようになった / 水が飲みにくい など。
嚥下機能のトレーニングとボイトレ 発声のための喉筋トレーニング

よく嚥下機能の活性化に有効とされる、発声や口の動かし方、顔、
滑舌のレッスンで口輪筋や舌を動かしたり、発声でのあくびのフォームや、身体を開く呼吸、そして声の高低など。
一般的にお医者さんがおすすめてしている嚥下トレーニングは、うたわないボイストレーニングでやる発声や滑舌の練習とすごく似ています。まぁ、喉の筋肉は、声の筋肉なので当然とも言えますね。
声帯閉鎖
さらにボイトレには声帯を意図的に閉じる「声帯閉鎖」
※参考文献
「声筋のすごい力」ワニブックス 渡邊雄介著
声の老化と身体の老化
つまり、声の老化は身体の老化のサインなのです。
声からの色んなサイン
身体は声を鳴らす楽器と言えます。その楽器から出た音声には、
滅多に食べない「菓子パン」を食べたことがバレたり、
身近なことでは寝不足や疲れがわかったり。
このように、声の変化・
ボイトレが認知症対策に有効な理由
ちなみに消費カロリーは、1曲歌うと10~20Kカロリーを消費し、1曲平均15Kカロリーで計算すると、20曲歌うと300Kカロリーにもなります。300Kカロリー消費するには、ウォーキングで60分程度必要になります。
さらに、脳を刺激する効果は目を見張るものがあります。発声は、脳トレの定番である音読と同様の効果があります。さらには、音程やリズムを合わせる必要があり、脳を高度に活用する必要があります。むろん、歌詞を覚えることで、記憶力の衰えを防げます。おおぜいで歌いに行くことにより、コミュニケーション能力も鈍らせません。歌に感情を込めたり、人の歌を聴いて感動したりと言った、泣いたり笑ったりという感情表現にも事欠きません。
また歌う際の腹式呼吸は心肺機能を高め、全身の血流を良くしてくれます。血流が良くなると細胞に栄養や酸素が十分に提供され、新陳代謝が促進されて、成長ホルモンの分泌が良くなります。成長ホルモンは、若返りホルモンとも言われ、老化防止に貢献するのは、言うまでもありません。
シブイオンガクスタヂオでは、対策に必要な、曲や課題、生徒さんの状態に合わせて必要なメニューをご提供いたしますので、
ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。